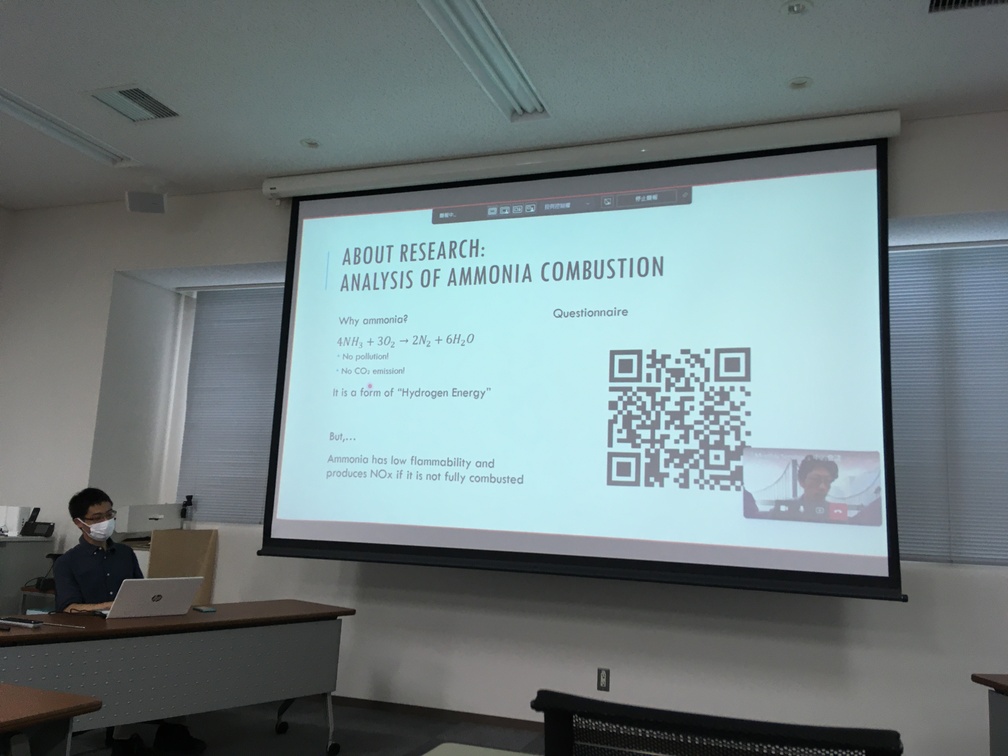最終更新日:2025年4月7日
京都大学アジア未来リーダー育成奨学金プログラム(AFLSP) は日本人学生ボランティアを募集しています. 特に,Team-Project Based Research (以下、T-PBR)では、AFLSP奨学金を受給する外国人留学生が3~5名のチームを組み,主に東アジアの地域を対象に,文化や国際関係,社会課題などについて討論し問題解決のための提言を行う研究を進めます.T-PBRに興味がある方は,KULASISから募集内容を確認いただき,期日までに担当者連絡先までご連絡ください.
先輩の声:ボランティアの体験談
- (2025/04/07) 農学研究科Nさん
修士課程2年から1年間日本人ボランティアとして参加しました。「A Study on Water Management Technique on Methane Emission Reduction in Rice Paddies in Japan(日本の水田におけるメタン排出削減のための水管理技術に関する研究)」というテーマに取り組み、4名の奨学生たちと共に研究活動を行いました。 ボランティアとして、国内のネットワークを活用して研究テーマに精通した方々を紹介しました。また、フィールドワークの際には、農家や研究者へのインタビューをアレンジしました。日々の研究室活動では経験できないプロジェクトマネジメントや異文化コミュニケーションのスキルが向上したと実感しています。私が考えるこのプログラムの醍醐味は、「Experience-Based Learning」です。私たちは、茨城大学と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)を訪れ、水田メタン排出削減に関する最先端の研究に触れる機会を得ました。研究者の方々が熱意を持って説明してくださる様子を実際に感じることができたのは、このフィールドワークがあったからだと思います。最終的には、プロジェクトの集大成として、これらフィールドワークに関するレポートを完成させました。 このボランティア活動を通して得た知識、ネットワーク、そしてチームワークの経験は、これからの生活に確実に役立つと感じています。日々の研究生活に「プラスアルファ」を求めている学生の皆さんには、ぜひボランティアに挑戦することをお勧めします。
- (2024/03/31) 農学研究科Aさん
修士1年の春から2年間参加させていただきました。活動内容としては、主に月に一度開催される奨学生たちの進捗報告会に参加してチームメンバーと交流を深め、研究テーマの検討、研究背景を理解するための文献調査、フィールドワークの準備などを行いました。私のチームは研究テーマを『日本における水稲の気候変動適応策への取り組み』と定めたのですが、活動の一環として兵庫県立農林水産技術総合センターの酒米試験地という全国唯一の酒米専門の研究機関への訪問を計画し、実現できたことは特に貴重な経験でした。最終的にはプロジェクトの成果を英語のレポートとしてまとめ上げるところまで達成することができ、とても充実した時間を過ごさせていただいたと感じています。 私はもともと留学に興味があり、英語力向上できたら良いな、くらいの軽い気持ちでT-PBRに参加しました。実際入ってみると、英語で、背景の違う学生同士で、一つのプロジェクトを進めるのは思った以上に大変なことでしたが、チームメンバーとの息抜きの時間や先生方の支えがあって、最後まで楽しく活動を続けることができました。春からはついに希望していた留学をスタートさせることができます。この留学を実現させる上でも、T-PBRを通じて強制的に英語を話す環境を作れたこと、すでに留学を経験している奨学生の友人ができたことは大きく私の背中を押してくれました。中でも、卒業後も大事にしたいと思える関係性がいくつもできたことは最も大きな財産だと思っています。また予想はしていなかったのですが、進捗報告会を通じていくつもの異なる専門分野の研究内容に触れることができ、これも毎度刺激になりました。数々の貴重な機会をいただきありがとうございました! 大学生活で「もう少し何かできるかな」と思っている人、留学に興味がある人、英語で交流を広げてみたい人、一度参加してみませんか?素敵な経験になるよう祈っています!